医師・患者の関係を巡って
-「医師と患者のライフストーリー」調査を振り返って-
村上 陽一郎
(「輸入血液製剤によるHIV感染問題調査研究委員会」副委員長)

1936年東京生まれ。国際基督教大学大学院教授、東京大学名誉教授。専門は科学史、科学哲学。東京大学教養学部卒。同大学人文科学研究科比較文学・比較文化専攻博士課程修了。東京大学先端科学技術研究センター長などを歴任。
主な著作に「生と死への眼差し」「科学者とは何か」「21世紀の『医』はどこに向かうか」「科学の現在を問う」「安全と安心の科学」などがある。
2010年4月より、東洋英和女学院大学(横浜市)の学長に就いている。
村上でございます。今、ご紹介がございましたように、MERSの大変膨大な仕事の、一応今日が締め括りということで、本日の講演会が催されることになりました。
ご覧になればお分かりの通り、医師と患者、それに調査に加わったアカデミアの研究者の方々、この三つ巴の様々な接点の中から、おそらくはこれまでに存在しないような一つの報告書ができあがりました。それが今ご紹介にあった「医師と患者のライフストーリー」という、非常に大きな記録として結実したことになります。研究会としては今日で終わるわけですけれども、この報告書は、医療の世界において「必ずしも終わりではなく、むしろ出発点でもあり得る」という性格のものだというふうに思われます。こういう大きな仕事を立ち上げられました「NPO法人ネットワーク医療と人権」の方々、そして調査研究に携わった研究者の方々に敬意を表したいと思います。
その中から、今日は「医師・患者の関係を巡って」というタイトルでお話をすることになりました。「『医師と患者のライフストーリー』調査を振り返って」という副題も付いております。しかし、この部分については、残念ながら私は歴史家の端くれとして、過去の話から解き起こすことが習慣になってしまっておりますので、まさに最も現代的な側面である、この「医師と患者のライフストーリー」を直接取り上げることは、最後のスライドにならざるを得ないというのが正直なところでございます。それはお許しを頂いて、後のディスカッションの場面で、またそういうところについての基本的な問題が様々な形で出てくるのではないかと期待しております。
今申しましたように、私は歴史家の端くれですので、どうしても古い時代から物事を始める癖がございます。そういうところから医師と患者の関係を考えてみますと、どの文化圏でも「医術者」、まだ「医師」ではないのかもしれませんが、医術に携わる人間というのは、おそらく人間文化の発祥から始まっております。
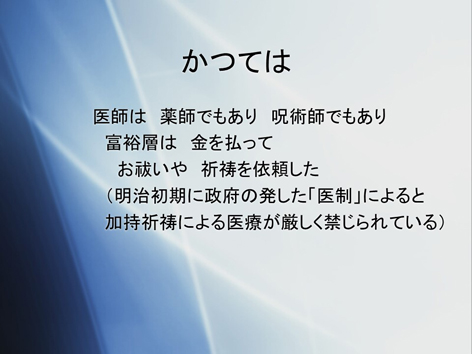
かつての「医師」とは、例えばスライドには「呪術」という言葉も書きましたけれど、今の医学とはおよそ無縁な「呪術師」であったりしました。これは現在の、いわゆる自然民族の中では未だにそうであります。スライドにもちょっと書いておきましたけれども、日本は、明治の比較的早い時期に、政府が「日本の医学・医療をヨーロッパの近代医学に切り替える」ということを明言し、かつそれをかなり強制的な権力によって実行した珍しい国というか、社会であります。その基になる文書に「医制」というのがございますけれども、そこには「今後、加持祈祷による医療の施術は厳しく禁じる」という文言が出て参ります。このことから「明治初期の日本でも依然として医術の中には加持祈祷が含まれていた」ということが読み取ることができます。しかし、基本的には「医学」と呼べる学問的体系があったわけではありません。
それから「薬師」ですね。「薬師」と書いて大和言葉では「クスシ」と読むと思いますが、「呪術師」や「薬師」、そういう人たちは、権力者や富裕層に雇われていました。ですので、この時代はまだ、いわゆる「医師・患者関係」というのは明確な形では出てきません。雇用者と被雇用者の立場のようなものが見て取れるとしても、「明確な形での医師・患者関係というのは、なかなか顕在化しない」という状況が長らく続いていたと思います。
よく引かれるのが、ヨーロッパの起源であるといわれる、古代ギリシャ、紀元前5世紀から4世紀にかけて活躍した医師で、「医聖」と呼ばれることもある、ヒポクラテスという人物で、「ヒポクラテスの誓い」というものがあります。
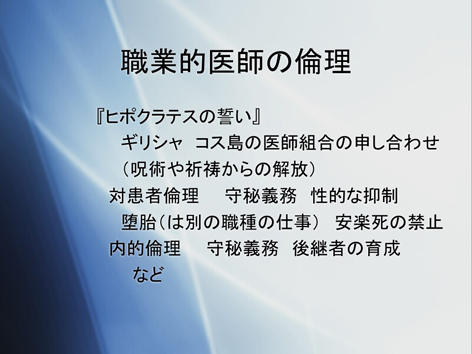
今でもヨーロッパ、アメリカの医学部の卒業式と言いますか、commencementでは、この「ヒポクラテスの誓い」が読まれる習慣が残っているところがいくつもあると聞いております。この「ヒポクラテスの誓い」というのは、ヒポクラテスというお医者さんの名前によって言い伝えられてきた誓いの文章なのです。これは基本的には、ヒポクラテスが生きていたコスという島の医師たちの組合の申し合わせ事項だったということになっております。
この誓いの中では、「患者に対する倫理」と、それから「医師同士の間で守るべき倫理」、これを私は「インターナル・エシックス」という言葉で呼ぶので、ここでは「内的倫理」という言葉にしておきましたが、これら二つの倫理が盛られております。「患者に対する倫理」というのは言ってみれば、医師が医師でない人との間の関係について考える場合の倫理的な綱領であります。「内的倫理」というのは、医師同士の間で守られるべき倫理綱領、あるいは行動規範のようなものを指します。
ご承知の方もたくさんあると思いますが、あえて言えば「医師として、患者ないしその家族に接した時に、患者やその家族について知ることのできた情報に関しては、これを他者には漏らさない」というのが有名ですが、面白いのは、そういうことがしばしばあったからこういう条項があるのだと思いますが、実際の文言は確かこんな感じだったと思います。自分が患家を往診によって訪れる時には、その門を潜る前に「自分は医師として患者の家を訪れるのだ」ということを自分に言い聞かせる、というような表現になっていたと思います。
つまりこれは、医師と患者の間の関係の中でしばしば性的な関係が結ばれる、ということに対する抑制だというふうに受け止められております。これは別に異性同士というわけではなくて、ギリシャですから男性同士の場合もいくらもあったと思います。それから「堕胎はしない」。これは倫理的に「堕胎が悪である」というよりはむしろ、「堕胎は別の職種の仕事であって自分たちのなすべきことではない」というような意味合いです。
だから「対患者倫理」というよりはむしろ「内的倫理」の方に含まれるべきものかもしれませんけれども、一応堕胎は対患者でもあるわけですので、「対患者倫理」に含まれます。それから、患者からいくらせがまれても致死量の毒薬は与えない、というような「安楽死の禁止」。こういった条項が盛られております。
「内的倫理」の方は、今は通用しない話ですが、古代社会における高度な職能技術者の集団の中ではしばしば起こっていることですが、「自分が先生から受け継いだ医術に関する知識と技術は、先生の直系の親族、もしくは特別に許された人だけに伝えて、他の人には決して漏らしません」という、そういう意味での守秘義務というのも語られています。自分たちが先生から学んだ、あるいは受け継いだ事柄については、簡単には他に漏らさないということです。
これはヨーロッパで言いますと、13世紀に「大学」という組織ができまして、この純粋に縦に受け継がれてきた知識やスキルというものが、学校組織の中で横に広がっていくという新しい時代を迎えるまでは、多かれ少なかれどこでも起こっていたことであります。
それから「後継者の育成」。これは今の技術や知識の伝承とも関わり合いがあるわけですけれど、どういうふうな形で後継者を育てていくかということについては、今も言ったように、かなり強い制限があります。こういったことが「ヒポクラテスの誓い」と呼ばれるものの中に凝縮された形で出て参ります。ここにはすでに、医師と患者の関係についてのある種の「意図的な考慮」というものが含まれている、というふうに考えることができます。
また、「ヒポクラテスの誓い」の中には出て参りませんけれども、ヒポクラテスが書いた様々な文献、あるいは本当に書いたかどうか分からないにしてもヒポクラテスの名前で伝えられている文献の中には、例えば「神聖病」という言葉が出て参ります。「神聖病」とは精神病のことでありますが、「神聖病について」という有名な文献の中には、すでに「呪術や祈祷からは医術を解放すべきである」というふうに読み取れる文言も出て参ります。「純粋に経験に基づいた治療というものを、いわば医術として独立した形で考える」という習慣がこのあたりには顕在化していると見ることができると思います。
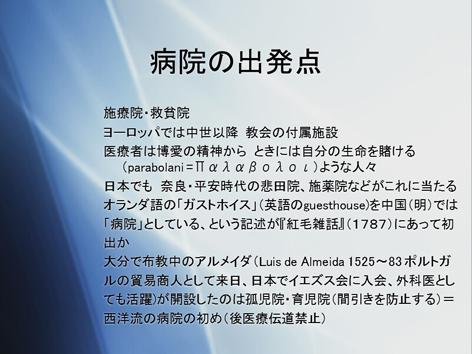
なぜ、この「病院の出発点」ということを申し上げるかと言いますと、私は1936年生まれですから今73歳です。私が子どもの頃は、「入院する」というのは、やっぱり何か非常に特別なこと、今でももちろん入院は特別なことなのですが、「忌むべきことである」と言いますか、病気で入院するわけですから当然喜ばしいことではないのは当たり前ですが、「入院する」ということ自体が、何て言うか、「単なる病気で病院に入る」ということではなくて、「何か特別な場所に収容される」という感じが残っているのです。
実は、私は73年の生涯の中で入院したことが一度もありません。深刻な病気に陥ったことはあるのですが、入院したことはないのです。だから、例えば姉なんかが入院せざるを得ないという状況は「何か非常に特別なことが起こっている」という印象を持っておりました。父親が医師であっても、そういう印象を持っておりました。病院に対する感覚というのは、いったいどこから来るのだろうか、ということを多少振り返ることも必要かと思い、ここでは「病院の出発点」ということを少しコメントしてみます。
そもそも病院というのは、基本的には施療院であったり救貧院であったりします。ヨーロッパでは教会の付属施設として、貧しい人たち、これは必ずしも病気でなくてもいいのですが、「貧困でまともに食事ができないような状態に置かれている人たちを助ける」というのが救貧院ですし、「多かれ少なかれ病気を持っていれば、その治療もある程度受け持つ」という、いわば「慈善事業として出発した」というのが基本だろう、ということになっております。
その点は、日本でもご承知の悲田院とか施薬院、聖徳太子が悲田院を建てたというのは俗説だということに今はなっているようですけれども、奈良・平安時代の悲田院とか、光明皇后の施薬院というのもやはり、「権力者が慈善のために困窮者を収容する」とか、あるいは「医師にかかれない人を収容する」というようなところとして同定されていた、というふうに考えることができるように思います。
そうすると、当然のことながら、「医療者というのはどういう人たちなのか」という疑問が出て参ります。ヨーロッパには「parabolani(パラボラニ)」という言葉があります。これはラテン語なのでしょうが、本来はスライドに書きましたギリシャ語「パラボロイ」という言葉から転化したものだそうであります。この「パラボロイ」というギリシャ語は、「自分の生命をも賭けてリスクに立ち向かう」というような意味を持った言葉です。そういう「パラボラニ」というような言葉が定着するように、必ずしもこれは医師とは限りませんが、医療者たちは文字通り博愛の精神を持って、つまり元々が慈善事業ですから、そこに携わっている人たちも、慈善・博愛の精神で、場合によっては自分の命を賭ける、というようなこともあり得たと言われています。
「病院」という言葉は、どうやら日本では18世紀に初めて使われ始めたらしくて、18世紀の終わり近くに出た「紅毛雑話」という、一般的にもわりあいよく読まれた本の中に、オランダ語の「ガストホイス」、これは英語式に言えば「ゲストハウス」でしょうが、これを中国・明では「病院」ということで呼んでいる、という記述が出て参ります。これがもしかすると初出ではないか、というふうに言われております。
それよりはるかに前、ご承知のキリシタン時代に、大分で布教中のルイス・デ・アルメイダという司祭がおりました。この人は、本来は貿易商人として日本にやって来たのですが、実は日本でイエズス会に入り、最後に司祭に叙されています。さらに、もともと外科医としても活躍していたわけです。この時代の外科医というのは、決してヨーロッパでは医師ではありませんでした。要するに、床屋さんであります。理髪医であります。理髪医としての技術を持っていたそうでありまして、彼がイエズス会に入って、まだ司祭として叙階される前に、豊後、大分地方で孤児院・育児院を開設いたします。この施設は、教会の門の横に箱を置きまして、「もし生まれた子供の間引きをするくらいなら、教会の門の脇に置いた箱に捨てていってほしい」ということをいわば公言しました。つまりこれは「堕胎」ではなくて、むしろ文字通り「間引き」でありますが、この施設は「間引きを防止する」という目的のために始められた施設として知られております。
これが西洋流、ヨーロッパ流の病院の初めというふうに通常言われておりますが、この後、イエズス会は医療による伝道を禁止することになりましたので、これは長続きいたしませんでした。ヨーロッパ流の病院としては、後にできる長崎の養生所というものが、今日まで、ある意味では繋がっている、本格的な病院の初めではないか、ということがよく言われます。
いずれにしても、お分かりの通り、「病院」というものの持つ意味合いが、こういう貧しい人、あるいはまともに医療が受けられない人のためにあった。「ホスピタル」という言葉自体も、あるいは「ホスピス」という現在の使い方とは少し違って、この「ゲストハウス」という意味が本来の意味であり、「ホテル」とも同根語であると言われますが、むしろ「病気の治療に専念するという場所ではなかった」というのが実情ではなかったかと思います。このことから、「病院の抱える矛盾」というのが私には見て取れます。
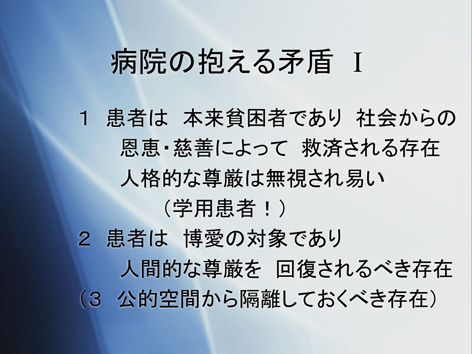
一つは、一方から言うと、患者は本来貧困者であります。社会からの恩恵や慈善によって、初めて救済されるべき存在であります。したがって、人格的な尊厳というのは病院の中では無視されやすい。さすがに今は「学用患者」という言葉は大学病院でも使われなくなったようですが、私が学生の頃は平気で「学用患者」という言葉が使われておりました。今日は養老(孟司)先生もここにいらっしゃるけど、たぶん養老先生の時代もそうだったと思います。「学用患者」という言葉自体が、ある意味では酷い言葉だと思いますが、要するに「大学病院に収容される限りはそのくらいのことは覚悟している」というのが昔の患者の心構えだったのかもしれません。
それはもちろん近・現代の話ですけれど、いずれにしても、一般的に言って病院というのは「そういう扱いを受けてもしょうがない人だけが来るところ」という社会的な一種の通念がありました。
一方、先ほどから申し上げているように、それは宗教的な付属施設であったり、そうでなくても「博愛」とか「慈善」という言葉を背景にして営まれている場所でありますから、本来的に人間的な尊厳がそこで回復されなければならないはずの場所でもあります。
もう一つ、この三番目のカッコに入れたものですが、これはだいぶ後になってからの話ですけれども「公的な空間からの隔離」。これは後で話しますが、病院というのは「患者さんを隔離しておくべき場所」という意味合いも持つようになります。こうした「病院」というものの持っているいくつかの矛盾する要素というのが、医師・患者関係の中に微妙に影を落としてきたのではないか、というのが私の仮説であります。
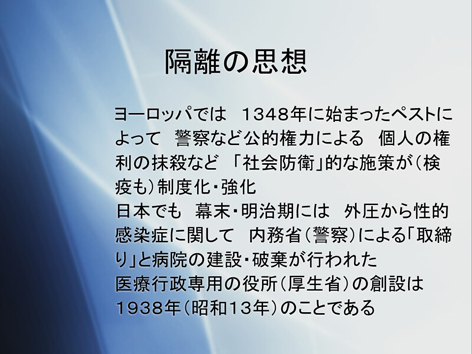
これは比較的後の話ですけれども、1348年から約30年間にわたって黒死病(ペスト)がヨーロッパ中を荒れ狂いました。ヨーロッパでは人口の3分の1が失われたとよく言われますが、この時はヨーロッパだけではなくて、アジアも中近東もみんな同じ被害を受けました。しかし、不思議なことに日本にはこの時期にペストが入ってきていない、あるいは少なくとも同定できるような被害は出ていません。これは大変不思議なことだと思います。
ちなみにもう一つ申し上げれば、19世紀の終わり近く、もう一度ペストの大流行、いわゆるパンデミック的な流行があるのです。ネズミを1匹何銭かで買い上げたりとか、ペスト菌を北里柴三郎が香港へ行って見つけただとか大騒ぎをするのだけれど、大騒ぎをしたわりには、日本は他の地域に比べて被害者(死者)の数は極めて少なかった。これはいったいなぜなのか、というのはどなたに伺っても誰も明確に答えを下さらないのです。ちょっと不思議なことだと思っております。
1348年にヨーロッパで始まったペスト、これはマルセイユから始まってイギリス、それから現在のロシアまで全面的に広がっていくわけですが、不思議なことに「感染」という概念は全くありませんでした。「病原体」という概念ももちろんありません。それから当時の医学で、「なぜペストが広がるか」ということに対する「唯一」じゃなくて「唯二」の要因説として、一つは「ミアスマ」というものがありました。これは大気汚染です。「どういう形で、なぜそれが起こるのか」というのはいろいろ説があって、例えば「火山の爆発によって大気に悪いものが放出されるんだ」とか、それから「地面の中の深井戸なんかから派生してきた毒を含んだ大気が人々を打ち倒すんだ」とかいうことが考えられてきました。
もう一つは何かと言うと、天文学的な理由です。天文学的な理由というのは、実はインフルエンザがまさにそうなのです。インフルエンザは、英語にすれば「influence」です。「influence」というのはもともと「影響」です。天文学的な、占星術的な意味合いで星から流れてくるもの「influence」で、それが地上にも様々な悪い「影響=influence」を与えている、と考えられてきました。インフルエンザという言葉はそこから来るわけですけれども、ペストもまたそうだ、ということになっていたわけです。
ですから、「人から人へ何らかの病気の原因が移っていく」という概念は、実は明確な形では、当時の医学の中では捉えられていませんでした。けれど、それにもかかわらず、「検疫=quarantine」という概念は存在していたのです。つまり、汚染地域から来た船は港外に40日間留め置いて、黄色い三角の旗を掲げて様子を見る、という方法を案出したのはこの時です。それから公安委員会のような、警察がとてつもない権力を発揮して、例えば患者の財産は全部没収するとか、それから死者の出た家は焼き払うとか、またペストで亡くなった死体は町中には決して埋めないで、郊外の特別なところへ放り出すとか、そして放り出しに行った係員は、しばらくの間は町には戻ってこないとか、そういう様々な警察的な、公安的な対策が、実はこの時期に講じられることになります。
これは、「感染」という概念がない、という前提に立つと非常に不思議なことです。つまり「公衆衛生」とか「社会防衛」とかいうような概念に立った時に、個人の権利、これは必ずしも患者ばかりではありませんけれども、「一人ひとりの個人の権利はほとんど重んじられない」という事態もここに起こります。
日本でも考えてみますと、幕末から明治にかけて最初の本格的な病院を建てるのですが、実は「避病院」でした。「避病院」という言葉、お聞きになったことのある方はもう今はあまりいないと思いますが、「避」というのは「避ける」という字です。要するに、そこに収容されると、もうほとんど治療は施されないことさえあります。そして、そこに収容していた人たちがみんな亡くなれば、その建物は全部焼き払われる、というようなことさえ実は起こっておりました。これは全て内務省、内務省というのは、今はもうありませんが、内務省の最も重要な行政組織である警察によって行われました。しかも性感染症に関しては、特別の収容病院が作られたりしております。
つまり、日本でもかなり長い間、医療行政というのは内務省、つまり警察の範囲内であって、医療行政専用の役所としては1938年(昭和13年)にようやく厚生省(現在の厚生労働省)ができました。私は昭和11年生まれですから、私が生まれたよりも後で、初めて厚生省という役所ができる、ということになります。このことは、主として権力によってこの「隔離」という概念、あるいは「囲い込み」ということが実行されていた、ということを意味しています。つまり、「病院」というのはそういう場所でもある、ということになっていきます。
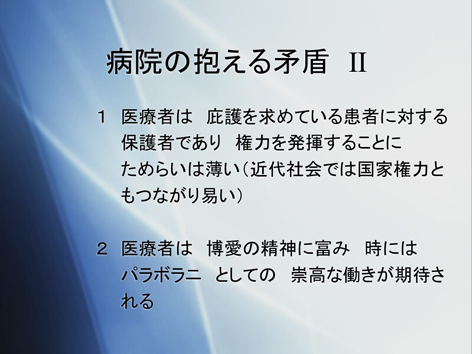
病院の抱える矛盾を別の面から見ますと、先ほどのⅠの側面に対応する考え方ですが、医療者の立場からすれば、「患者というのは庇護を求めている。自分たちはそれに対する保護者である。権力を発揮するということにためらいは必ずしも厚くない」ということになります。
近代社会では、特に「国家権力とも繋がりやすい」というところがあって、なおさらそういう側面を助長させる因子が含まれています。それと同時に、医療者というのは、先ほどのもう一つの面、博愛の精神に富んで、時には「パラボラニ」、つまり「自分の命さえ投げ出すことがあり得る」という崇高な働きが医療者に期待されているし、また事実、医療者の中にはそれを自負している、あるいは自認している、という側面が窺われます。これらの相反するような考え方が共存する場所として存在するのが「病院」というところであり、あるいは病院における医師と患者の関係の背後にある前提である、と申し上げても差し支えないように思います。
つまり、医師・患者関係というのはこういう背景の中で問題視されるようになった、と考えることができるのではないか、というのが私の仮説でございます。
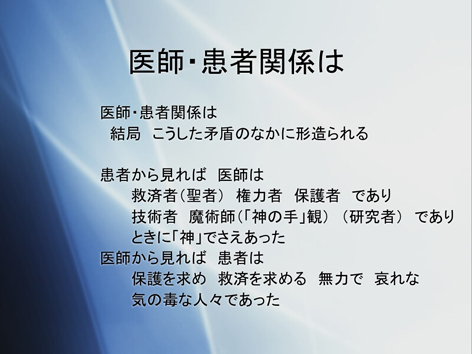
そうすると、こういう関係の中では、患者から見れば、場合によっては、医師は「救済者」であり「聖者」でもあります。シュバイツァーが「ランバレネの聖者」と言われたこともありますし、時には「神」でさえあったとさえ言えるでしょう。しかも権力を持っている存在であり、保護してくれる人であり、場合によっては技術者でもあります。これは外科医の場合には明らかにそうですね。
ヨーロッパ的な伝統で言えば、日本でも漢方は外科を重んじませんでした。昔は内科の医者のことを「本道」と申しました。そうすると外科は「外道」になるわけで、今考えると酷い話なのですが、それでもヨーロッパの場合の外科医は、先ほども申しましたように、医師の組合の外にあった職人の、親方・徒弟関係の中で育てられる技術者でありました。そういう意味では、外科医は文字通り「技術者」であり、あるいは「魔術師」でさえありました。19世紀以降には、医師にはもう一つ、「研究者」という側面も持つようになります。
一方、医師から見れば、先ほどから申し上げているように、患者というのは「自分たちに保護を求めている、救済を求めている、無力で、無知で、哀れな、気の毒な人々」であり、だからこそ博愛・慈善の対象になる。これは別に悪意でなくても、むしろ博愛の立場からいっても結局そういうことになるわけですね。そうでなかったら、「慈善」という概念は出てこないわけですから。そういう中で育まれてきたのが、私たちが過去において持っていた医師・患者関係であります。「過去において持っていた」というのは、あたかも過去の話のように言いましたけれど、これは必ずしも完全に過去になったわけではない、というのが現状であります。
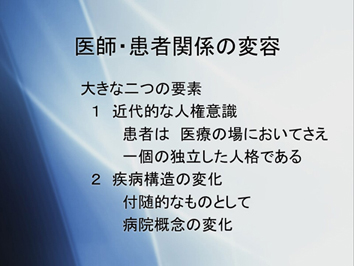
しかし、その関係の中には確かに大きな変容を見て取ることができます。私は二つの大きな要素を指摘することができるのではないかと思います。言うまでもなく、一つは文字通り、「患者の権利」、人間としての基本的な権利としての人権意識というものであります。二つ目として「疾病構造の変化」、そしてこれに付随する「病院」という概念の変化というものが挙げられます。
つまり「病院」という空間の持っている意味の変化というものが、この医師・患者関係に非常に大きな変容をもたらしたと言えるのではないでしょうか。言ってみれば、こういう一つ目の人権意識のようなものに必ずしもセンシティブじゃないような医療者にとっても、この二つ目の要素というのは、やはりかなり大きな意識変革のモチーフになっている、というのが実際のところではないかと思います。
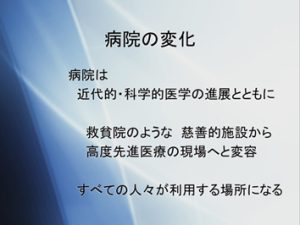
近代的・科学的な医学が19世紀以降のヨーロッパを出発点として進展していきますと、「病院」は、救貧院のような慈善的な施設から高度先進医療の現場へと変容していきます。しかも当然のことながら、そういう性格の変化から、利用する人々は、慈善の対象になるような人々だけではなくて、むしろ全ての人々が利用するような場所になっていきます。現代の日本では「大きな病院にあまりにも多くの人々が利用しすぎる」というのが問題になっていますが、それはともかくとして、少なくとも、「病院」とは全ての人々に開かれた場所である、という概念に少しずつ変化をしていく、というのが一つのポイントですね。
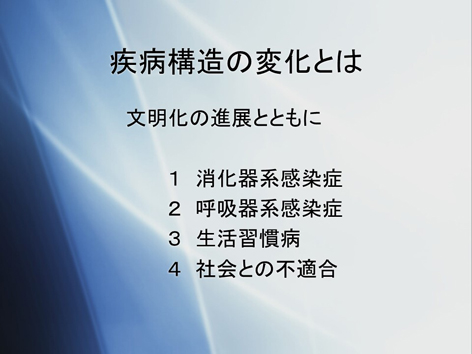
それに対して「疾病構造の変化」について、これはあるイギリスの疫学者が言っていたことで、なかなか面白いのですが、彼は「文明化の進展とともに、社会全体が苦しむ疾病の主だったところに大きな変化が生じるのではないか」という仮説を述べています。文明の程度が極めて低い状況の中では、消化器系感染症によって人々がどんどん亡くなっていく。死亡原因の主だったところは消化器系の感染症である。そして、少しそれが克服されると、今度は呼吸器系の感染症が社会の主たる疾病になっていく。そして、さらにそれが克服されると、次は生活習慣病が中心になる。
そしてそのさらに先には、その社会に住む人々が「自分の生きている社会に対して必ずしも適合感を持てなくなる」という事態に陥ることが医療上の問題点として浮かび上がるような社会というものが待っているのではないか、ということです。もしかすると日本はこれで言うと、今は3と4のちょうど中間ぐらいにある、というふうに見ることができるかもしれません。

上の表は死亡原因上位5位の経年変化を示したものであります。経年と言っても年ごとではありませんけれども、出発点は大正9年、1920年から始まります。実はこの前に明治時期がありますが、ご承知の通り、明治時代の人々が最も恐れたのは消化器系感染症、特にコレラであり、今はもう死語になってしまった赤痢であります。
「医療が進歩したから」というよりはむしろ「衛生環境が少しずつ整ってきたから」と言った方が正しいと思いますが、消化器系感染症がある程度克服されると、1935年ごろから、今度は肺炎や気管支炎、それから全結核が死亡原因の上位に出て参ります。結核には泌尿器結核もあれば皮膚結核もありますし、カリエスなどもよく聞きますけれども、最も多いのは肺結核です。それを呼吸器系の感染症に入れれば、肺炎とともに1位・2位を独占した時代がしばらく続きます。
その後、1951年からは脳血管疾患が1位に躍り出まして、全結核が2位に下がります。脳血管疾患は、当時の言葉で言えば「脳溢血」が多かったと思いますが、つまり脳出血ですね。現在で言えば、脳梗塞なんかも含めてだと思います。
やがて1982年からは悪性新生物、いわゆる「がん」がトップに躍り出て、脳血管疾患が2位に下がりました。それからまもなく1985年には、3位だった心疾患、つまり心筋梗塞等のことですが、心疾患が2位に上がります。
その後、現在も、多少の入れ替わりはあったとしても、基本的には悪性新生物が1位で、心疾患が2位、脳血管疾患が3位という状況が続いています。あと、肺炎・気管支炎はなかなか減ってくれないのですが、これはおそらく高齢疾患とも関連していて、高齢者の死亡原因のかなりの部分を占めています。
また、高齢者が風邪なんかで亡くなっても、死因として「肺炎・気管支炎」と医師が診断書を書くということもあって、おそらくこれは高齢社会の中では完全には克服されない疾患として残るだろうと思います。
5位の事故についてなんですが、ご承知の通り、もう数年すると自殺の方が事故より多くなるのではないか、と言われています。交通事故が劇的に減っていますし、自殺はじりじりと上昇しておりますので、5位に自殺が姿を現すのではないか、と心配されているわけです。
この表をご覧になっても、先ほど申し上げた「自分の生きている社会に対して必ずしも適合感を持てなくなる」という事態というものが、ある程度裏書きされているように思います。
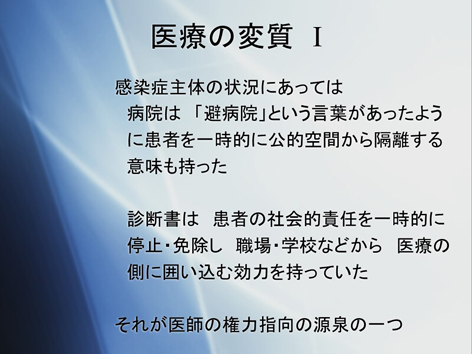
そこで私が申し上げたいのは、「疾病構造の変化に伴って医療の質は変わってくる」ということです。これはやはり指摘せざるを得ません。消化器系感染症にしても呼吸器系感染症にしても、いずれにしても感染症主体の状況の中では、「病院」というのは、「避病院」という言葉さえあったように、「患者を一時的に公的空間から隔離する」という意味を持っていました。
そして、医師が出す診断書というのは、患者の社会的な責任を一時的に停止・免除して、例えば職場や学校に通うことを「しないで済む」と言うと変な言い方ですが、あるいは「してはならない」と言ってもいいかもしれませんし、どちらのケースもあり得るわけですが、「医療の側に患者さんを囲い込む効力を持っていた」というわけですね。
つまり、「医師のさじ加減一つで、患者さんは社会的な責任や義務から解放される」ということも一時的にはありました。また逆に言えば、「社会的な責任を果たすことを禁止される」ということにもなります。しかもその時には、多くの場合、「病院なら病院」という医療の側に囲い込まれます。その判断を医師が「することができる」、あるいは「しなければならない」、そしてこれは「医師の責任でもあり義務でもある」ということになります。
これは言ってみれば、「患者さんの生活に関して、医師が権力的な判断を下すことができる、あるいは下さなければならない」という事態を示しています。
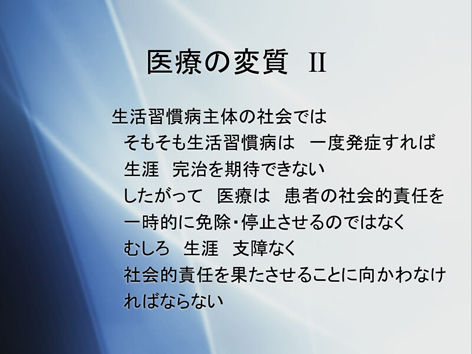
では、生活習慣病主体の社会ではどうなるのでしょうか。生活習慣病は、基本的には一度発症すれば生涯完治を期待できない病気であります。
例えば糖尿病。1型はともかくとしても、通常の糖尿病は、様々な遺伝的要素と、それからそれまでにその人が送ってきた生活との相互作用の中から発症します。そうすると、その病因は「その患者さん自体の中にある」ということになります。
つまり、患者さんの性格、酒が好きだとか、喧嘩っ早いというようなものと同じように、患者さん自身が持っている内的なものとして病因が存在しているのです。だから、感染症のように「外から何か悪いものが入ってきて、それを追い出せば問題は解決する」というような病気ではなくて、「患者さん自身の属性の中に含まれてしまうような病気である」ということになるわけです。
がんの場合には、摘出手術をすれば完治するということもないわけではないでしょうし、がんも生活習慣病に少なくともある程度囲い込める病気だということにすれば、完全にそうだとは言い切れないかもしれませんが、一般的にはこうなります。
したがって医療は、患者の社会的な責任を一時的に免除したり停止させたりするわけにはいきません。むしろ医療は、「患者が生涯支障なく社会的責任を果たさせることに向かっていかなければならない」ということになります。
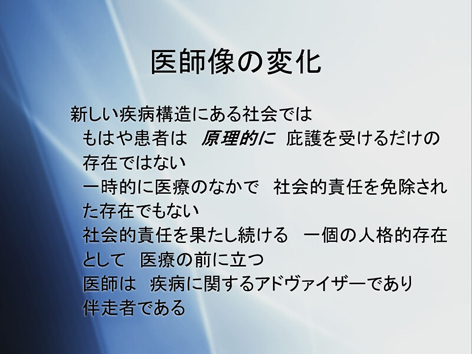
そうすると、こういう疾病構造の社会の中では、患者は受け身的に庇護を受けるだけの存在では原理的になくなります。「病気」という概念そのものがすでに「そうではない」ということを言い立てていることになります。そして、一時的に医療の中で社会的責任を免除された存在でもなくなります。社会的責任を果たし続ける一個の人格的存在として、医療の前に立っていることになるわけです。
したがって、よく言われることですけれども、医師は、「疾病を抱え込みながらも、生涯一人の人間として社会的責任を果たしたり、人間として生きていったりすることを助ける存在、あるいはアドバイザーであったり伴走者であったりする」という役割にかなり大きく変化をせざるを得ません。それが現在、私たちの社会が迎えている一つの側面であります。
もちろん感染症もあるわけですし、全ての医師がそうなったわけではありません。完全に構造が変化した、とは言い切れないにしても、主たる社会状況としては、先ほど申し上げたような「救済者」であったり「権力者」であったり「保護者」であったり「魔術師」であったりするような医師ではなくて、「アドバイザー」であり「伴走者」であるような役割が非常に強調される時代を迎えている、というふうに申し上げられると思います。
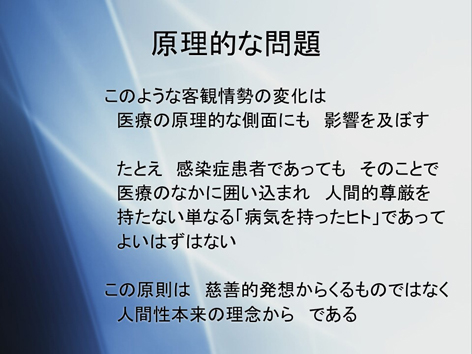
こうした客観的な状況の変化によって、先ほど申しましたように、本来の原理的な側面にも、やはり医療者は好むと好まざるとにかかわらず気づかざるを得ません。
つまり、医師の庇護の下に、あるいは医療の保護の下にしばらく囲い込まれるはずの感染症患者であっても、原理として、「人間的な尊厳があまり重んじられないような病気を持った人」としての存在であって良いはずはありません。「人間としてそういうことであって良いはずはない」という考え方が、言わば文字通り、好むと好まざるとにかかわらず、医療者の間にも反省として広がりつつあります。
この原則は、慈善的発想から来るものではありません。つまり「慈善」とか「博愛」とか言って、「患者さんというのはかわいそうな存在であり、慈善的な配慮をされなければならない。そういう意味で尊重されるべき存在である。だから人間性も温かく保護してあげなければならない」という、そういう発想ではなくて、人間性本来の理念から、この原理的な、人間としての基本的な、それこそ「人権」なんですが、そういうものを尊重する、という立場に意を払わなければならない、ということが医療者の間にもようやく広がってきました。
したがって、様々なところで「患者の権利」というようなことを言われるようになります。
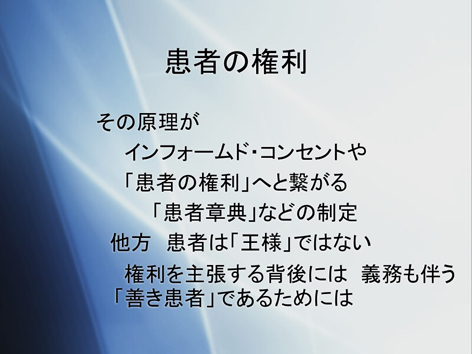
「東京都立病院倫理委員会」という委員会があって「患者の権利章典」というものを編みました。これは、「病院のような医療が囲い込んでいる空間の中で、患者の基本的な人権はどうやって守られるべきなのか」ということに関して、様々な論点を簡潔に示した権利章典です。ご承知のインフォームド・コンセントなどにも触れておりますが、アメリカの場合なんかですと、もうすでに「I・C=インフォームド・コンセント」の「C」が「コンセント」ではなくて、「チョイス」になっているとさえ言われるような状況が生まれてきています。
その権利章典の中でも指摘したのですが、患者といえども「お客様は神様です」というのではなくて、王様でも神様でもなくて、そういう権利を主張する背後には、当然のことながら義務も伴います。
例えば、船橋医療センターというところは、入院する患者さんには必ず患者さんの権利を記した文書を配っておられます。その中にこういう項目があります。私は大変面白いと思ったのですが、「看護師や医師が何らかの業務について非常に忙しくしている時には、お声をおかけになるのはちょっと遠慮してください」ということが書いてあるのです。患者さんの方に対する、そういうお願いも含まれているわけですね。実際私たちは、例えばワンマンバスで運転手さんが一生懸命運転している時に声をかけるのは遠慮しますよね。それは常識なわけでしょう? でも病院という空間の中では、時々その常識が働かないことがあります。
私が看護師さんなんかに対してお話をする時には、「あなたが何か大事な仕事をしている時、例えば点滴の名前を書いている時だとか、仕分けをしている時ですね。もしそういう時にナースコールがあったら、あなたはどうしますか? ナースコールに飛びつきますか?」という問いかけをします。私は必ず「そういう場合は心を鬼にしてでも、そのナースコールは誰かに任せるか、少なくとも少し待ってもらって、今やっている仕事をとにかく終わらせてください」ということをお願いします。なぜなら、事故が起こる時、アクシデントやインシデントが起こる時というのは、まさにそういう時なのですね。
つまり、やりかけている仕事を途中にして別のことをして戻ってきた時に、「いったい今、何をどこまでやっていたのか」ということは、必ずしも誰もが明確に覚えているわけではないのです。インシデントが起こるとすると、本当にそういう時に起こるわけですね。
そういうことを積み重ねていきますと、患者側にもまた「いろいろな状況を見極めつつ要求をする」という義務が発生します。そういうようなことを含めて、今は「モンスター・ペイシェント」なんていう概念も喧伝されるわけですけれども、「良き患者であるためにはどうするのか」ということも同時に社会教育の中で必要になってきている、と私は考えております。
こういうことを言うと非常にひんしゅくを買いますが、「高校は3月で終わり、大学は9月入学にしましょう」と私はよく申し上げます。「全ての人間が徴兵のような形で、その半年間に医療機関で働く、ということをやったらどうか」ということです。病院にとっては大変迷惑な話だと思うのですけれど、つまりこれは患者教育です。誰しもが将来患者になるわけですから、これは患者教育にもなる、ということを提案したのですが、誰もまともに扱ってくれませんので、今のところ単なる提案に終わっています。しかし、真面目に私はそういうことが必要なのではないか、と考えております。
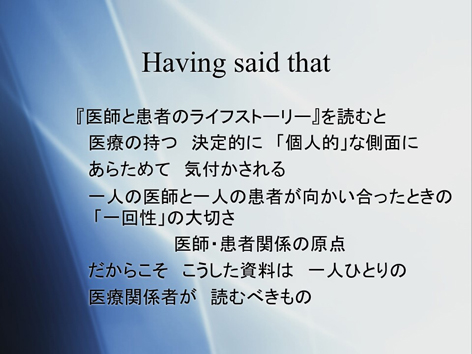
これが最後のスライドですが、英語ではよくこういう時に「Having said that」という言葉を使います。なかなか含蓄のある言葉だと思います。どういう意味かと言うと、例えば会議なんかで何か提案があったとします。それを「大変結構なものです。そういう提案をしてくれたことに対して敬意を表します」と一応言っておいて、そしてその次に使う言葉が、この「Having said that」なんですね。「私はこういうことを言いましたけれども…」ということです。日本語にすると何でしょうかね。「さはさりながら」というような感じでしょうか。あるいは「それはそれとして」と言うのでしょうか。
とにかく「さはさりながら」、つまりここまで申し上げたことは一般論として私は必ずしも間違っていないと思っています。しかし、ここで積み重ねられてきた一つの成果である「医師と患者のライフストーリー」を皆さん実際に手にとってお読みくださればお分かりになると思うのですが、結果的には、医師と患者の関係というのは、最終的には、文字通り個人的な事柄であります。
日本では「小児科」というと、子どもがかかるお医者さんであり、病院であれば科であるわけですね。でも、血友病を持っておられる患者さんというのは、子どもの時から始まって、思春期を経て成人になっても同じ先生のおられる小児科に通い続けなければならないわけです。これは大きな問題でもあるのですね。そういう時にいったい医療の側はどうすべきなのか。大倉病院が国立成育医療センターになった理由の一つはそこにあったわけです。
この国立成育医療センターは言ってみれば、「小児科にかかっていた患者さんたちの年齢が上がっていって小児科の扱いではなくなった後でも、ちゃんと同じ先生に面倒を見てもらえるように」というプリンシプルの下に作られた、という理念として言われております。それが一つの非常に大事な問題なのですけれども、たぶん血友病で苦しんでおられる方々は皆さん、「どこかで切り替えなければならない」という時期を今までは迎えられてきたのではないかと思います。
そういうことも含めて、一人ひとりの患者さんと一人ひとりの医師が向き合った中での極めて個人的な、一回的、一回というのは時間的な系列の意味ではなくて、出会いが一回であった、ということですが、そういう一回的な出会いの中で培われていく非常に濃厚な個人的空間に対して、今までお話ししてきたような一般論とそういう個別論とがどういうふうに切り結ぶのか、ということについて、私は実は答えがないのです。
今回の「医師と患者のライフストーリー」を読ませていただくと、なおさらそこのところの繋ぎをどういうふうに考えたらいいのか、思いを巡らさずにはいられません。繰り返し申し上げますが、医療一般として考えている時、これまで申し上げたことは決して、それほど的外れではないと思います。しかしそういう状況の中で、一人ひとりの患者さんと一人ひとりの医師、あるいは医療者とが出会った時に、それがどういうふうに問題を解決するのか、あるいは問題を作り出すのか、またその中で解消されるべきものがあるのかどうか、ということについては、まだまだ解決には程遠いと思います。
むしろ最初に「これは出発点だ」と申し上げた理由はそこにあります。解決はほど遠い、でも我々は、特に医療者の方々には、こういう膨大な資料を読むのは大変だと思いますけれど、どこかで向き合って読んでいただいた上で、これから医療者が患者さんと向き合う時の一つの礎として利用していただければ非常にありがたいのではないか、ということを最後のメッセージとして付け加えさせていただいて、私のお話の締め括りにさせていただこうと思います。
ご清聴ありがとうございました。
