若生 治友
はじめに
MARS設立の大きな目的、調査研究事業として「輸入血液製剤によるHIV感染問題調査研究委員会(委員長:養老孟司氏、通称:養老委員会)」を立ち上げた。その委員会初期メンバーである蘭由岐子氏と山田富秋氏が2024年3月末をもって所属大学を定年退職することとなった。
お二人の所属大学において退職記念講義が行われ、蘭氏の「社会調査と<わたし>」と山田氏の「フィールドワークと学問を語る―戸惑う、もがく、楽しむ―」に参加したので、養老委員会に関連して印象的な内容について概要を紹介する。
概要
1.蘭 由岐子氏 最終講義
「社会調査と<わたし>-ハンセン病研究と薬害HIV研究の経験から」
日時:2024年2月27日(火)15:15〜17:00
会場:追手門学院大学 安威キャンパス 5606教室
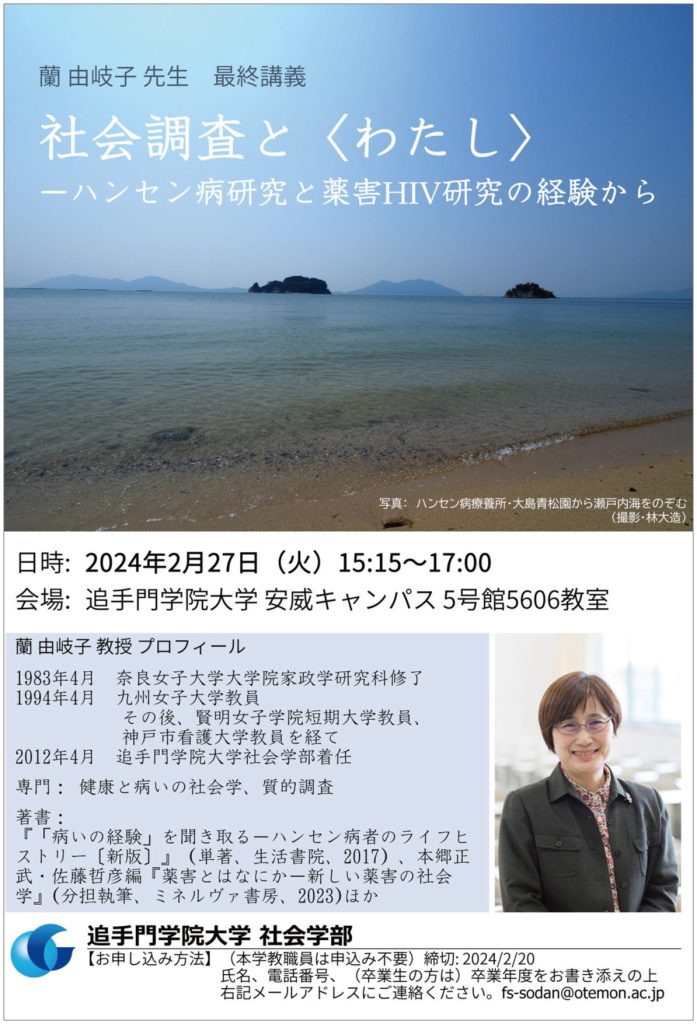
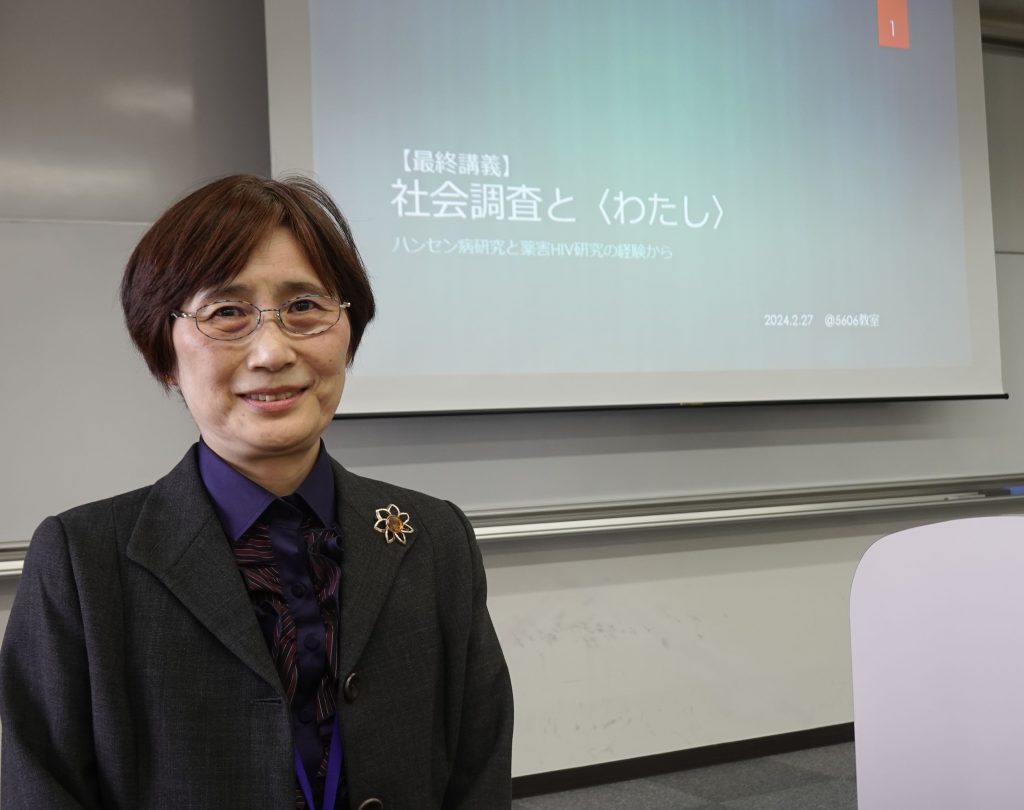
2.山田 富秋氏 退職記念講義
「フィールドワークと学問を語る―戸惑う、もがく、楽しむ―」
日時:2024年3月8日(金)13:30~17:30
場所:松山大学樋又キャンパス H2A
司会:石川良子(立教大学)、根本雅也(一橋大学)
登壇者:
・佐藤郁哉(同志社大学):「エスノグラフィーと参与観察のあいだ」
・田中雅一(京都大学名誉教授):
「オートエスノグラフィーにとってフィールド(ワーク)とは何か?――文化人類学からの視点」
・山田富秋(松山大学):「薬害エイズ事件とハンセン病を調査する――言い分は even」
コメンテータ:水上英徳(松山大学)、蘭由岐子(追手門学院大学)
1.蘭由岐子氏 最終講義
常勤職員となって30年の研究生活・人生を振り返った内容であった。
ハンセン病研究の紹介では、実際のハンセン病者の語りを引用しながら、実は調査者の方が聞き取り対象者から見定められていることに愕然とし、また研究を遂行する上での自身の迷い・葛藤をお話しされた。
薬害HIV研究の紹介では、ハンセン病研究の経験を踏まえ、複数の研究者チームによるインタビュー調査の難しさ、疑問を呈し、ジェンダーの課題にも言及された。

1)ハンセン病研究の現場での印象
・それまでハンセン病の文献では、自身の過去を隠したり偽名を使ったりする病者像や療養所の病者を人とも思わないような対応が描かれてきた。一方で、実際の聞き取り調査で訪れた「目の前の病者」は、詳細に人生を語り、療養所への思い・考え・感情を正負両面から語っていた。
2)調査の過程での葛藤
・ハンセン病者の聞き取りで(出された)「お茶を飲むかどうか」をチェックされていたことを後から知る。他の研究者はお茶に手を出さないと聞き、調査されているのは実は自分たちの方であり、ある意味、試されているのだと痛感した。
・堕胎された女性と子育て中の自身との間で、振る舞い方や自分にできること、研究の意味を悩んでいた。
3)薬害HIV研究とハンセン病研究の比較と戸惑い
・薬害HIV訴訟はハンセン病訴訟の前例となった。
・薬害HIV研究は、訴訟言説を当事者自身が脱構築する研究で「薬害エイズ」を相対化した。
・ハンセン病研究では医学的知識は医学会から獲得していった。一方で薬害HIV研究では、他の経験豊富な調査メンバーは(調査時に)「教えてもらえばいい」という感覚であったが、蘭氏は違和感を覚えていた。
・医師は男性研究者の話を聞いて返答する傾向があり、蘭氏が質問をしても男性研究者が別な質問を被せてくるなど、複数の研究者間でインタビューの主導権争いのような場面があった。
・患者の母親への聞き取りの時には、蘭氏は強く感情移入してしまい、聞き取りを続けられなくなった経験を語られた。
4)人生を振り返って
・「主婦」からの脱出を図って学び直しをした結果、ライフストーリー・インタビューに関わり、研究者生活がスタートすることになった。自身は30代半ばからのスタートであり、だいぶ遅れていたことを振り返っていた。
・かつての知人女性が血友病類縁疾患(凝固異常症の一つ)であったことが、今思えば薬害当事者と縁があったのだと感じていた。
2.山田 富秋氏 退職記念シンポジウム
山田氏を含む3名の方からの発表の後、コメンテータからの発言・質問を受ける形で、シンポジウムは進行した。

2.1 山田 富秋氏:「薬害エイズ事件とハンセン病を調査する――言い分は even」
1)ライフストーリー研究の始まり
・2000年に好井裕明氏(現・摂南大学)らから呼びかけられ、蘭由岐子氏と種田博之氏(産業医科大学)らと共に養老委員会に参加したのがライフストーリー研究の始まりでもあった。
・養老委員会に参加した同じ頃、京都精華大学の院生が始めたハンセン病療養所でのインタビュー調査に同行したことをきっかけに、ハンセン病に関わることとなった。
・それまでの調査研究の手法としての会話分析に物足りなさを感じ、ライフストーリー研究に転換していくこととなった。薬害HIV調査研究では複数の研究者からなる“チームプレー“となっていった。
2)薬害HIV調査研究の失敗と再構築
・「第1次報告書」での失敗は、マスコミ言説を元にしているだけでなく「生きられた経験」に適合しないというものであり、「第1次報告書」に対して、医師ばかりでなく薬害被害当事者からも批判を受けたことが衝撃であった。
・この失敗を反省し、調査対象者の世界にどのようにアクセスするのか、それを体験しなければならないと感じた。相手を知るためには、現場を知らなければならないということだった。
・長い時間・年月をかけて調査対象者との関係を確立していくことで初めて文脈を理解し、「言い分」が腑に落ちる。

2.2 コメント:蘭 由岐子氏:
1)共同研究「薬害HIV研究」におけるフィールド
・語り手の「死」も含む「存在」自体の重さを痛感した。
2)ライフヒストリーのフィールドでの「戸惑い(もがき)」
・最小限のフィールドである対話の場面で自分の戸惑いは起こった。
3)フィールドワークを「楽しむ」
・調査は、さまざまな人生があるということを知る最前線。自分自身が「耕される」感覚だった。
・調査対象者と研究者メンバーと共に人生を経る楽しみがある。

感謝を込めて
蘭由岐子さん、山田富秋さんには養老委員会の初期メンバーとして関わっていただいてから20年以上、初期調査が暗礁に乗り上げた時も粘り強く研究を継続していただき、心から感謝申し上げます。
養老委員会の最終報告書「医師と患者のライフストーリー」を発行後も、新たに加わった研究者や私たちに的確なアドバイスをいただきました。
現在もなお、薬害調査研究として基盤研究(B)「薬害をめぐるコンフリクトと制度化−社会秩序形成過程にみる薬害の社会学」 (代表:中塚朋子氏)が続いており、国内外での発表企画やこれまで聞き取りを行なってこなかった人々への新たな調査なども進行中です。引き続きご協力を仰ぎたいと思います。
昨年2023年4月に「薬害とはなにか-新しい薬害の社会学」を出版できたのは、お二人の存在・支持が大変大きかったと考えます。重ねて御礼申し上げます。
